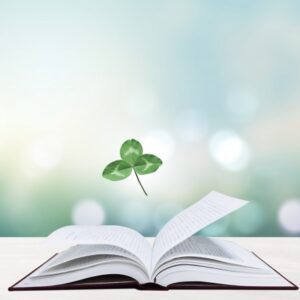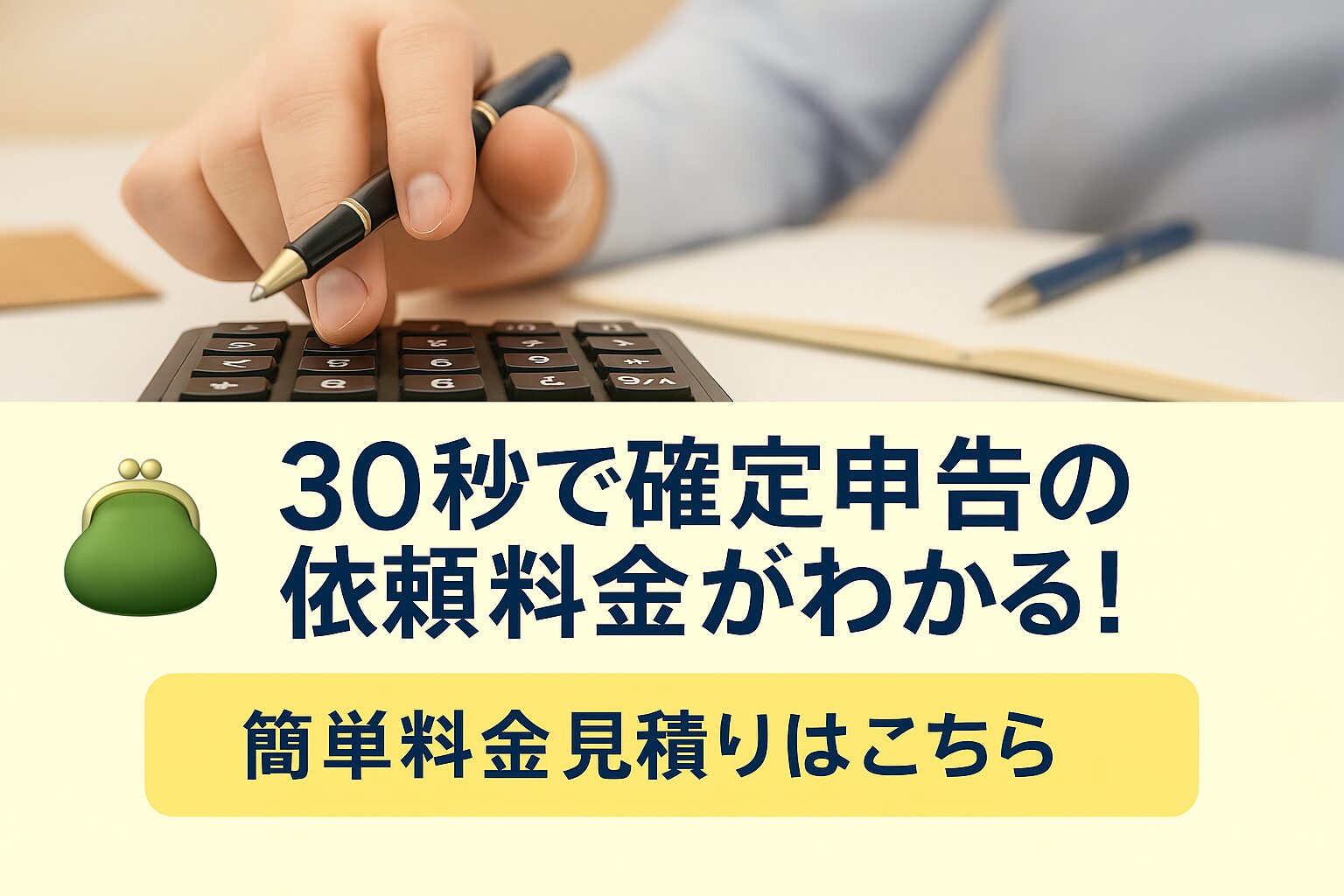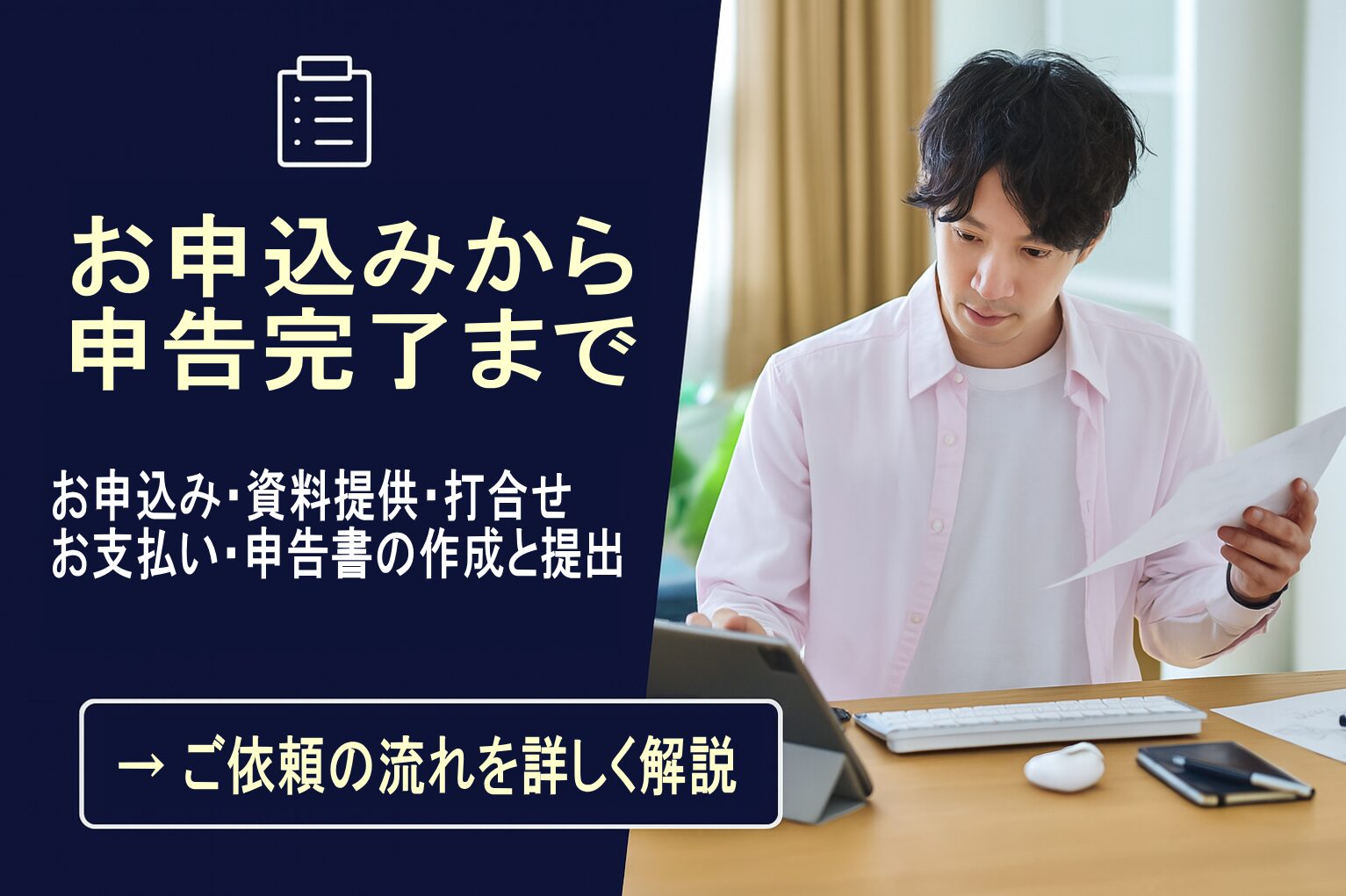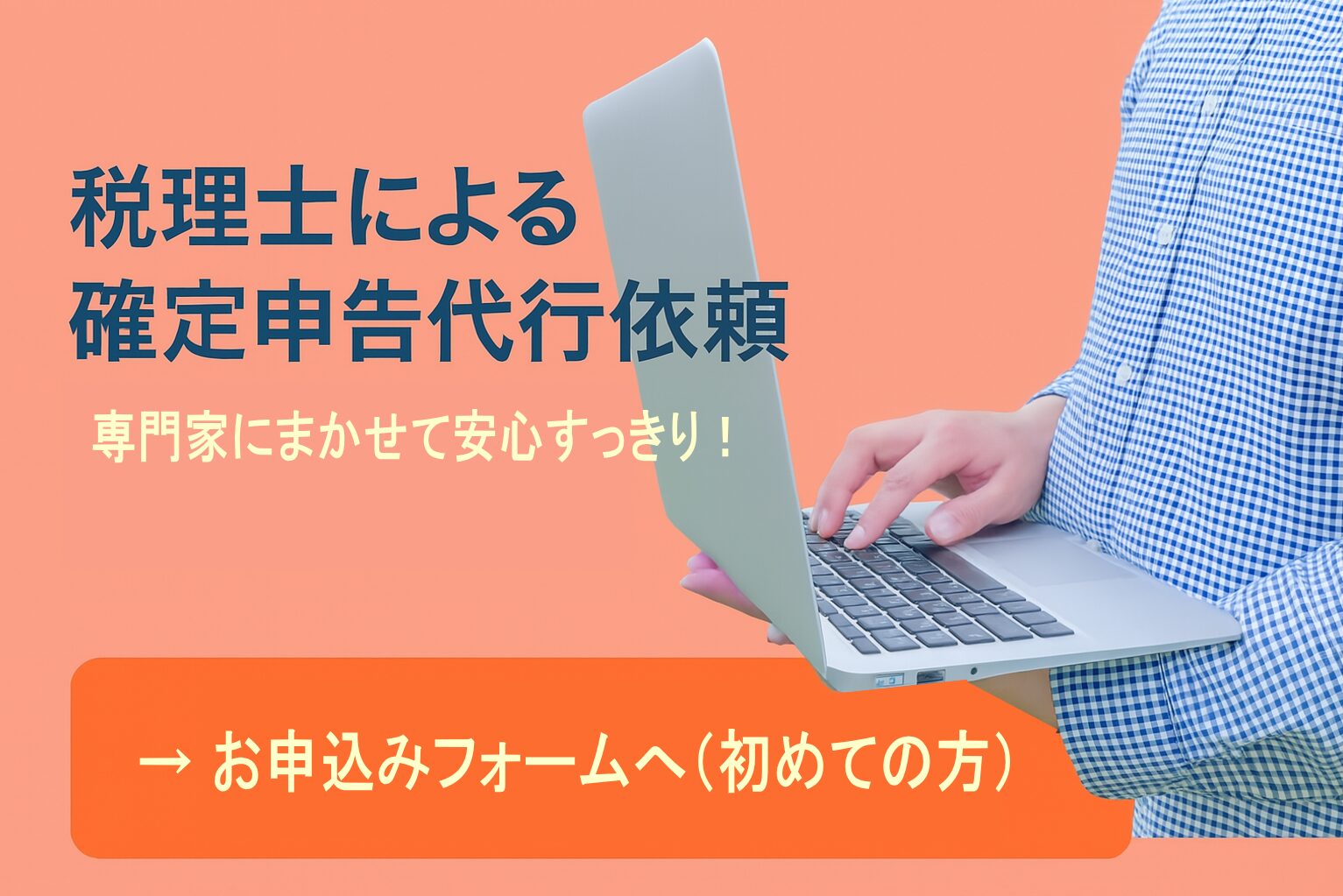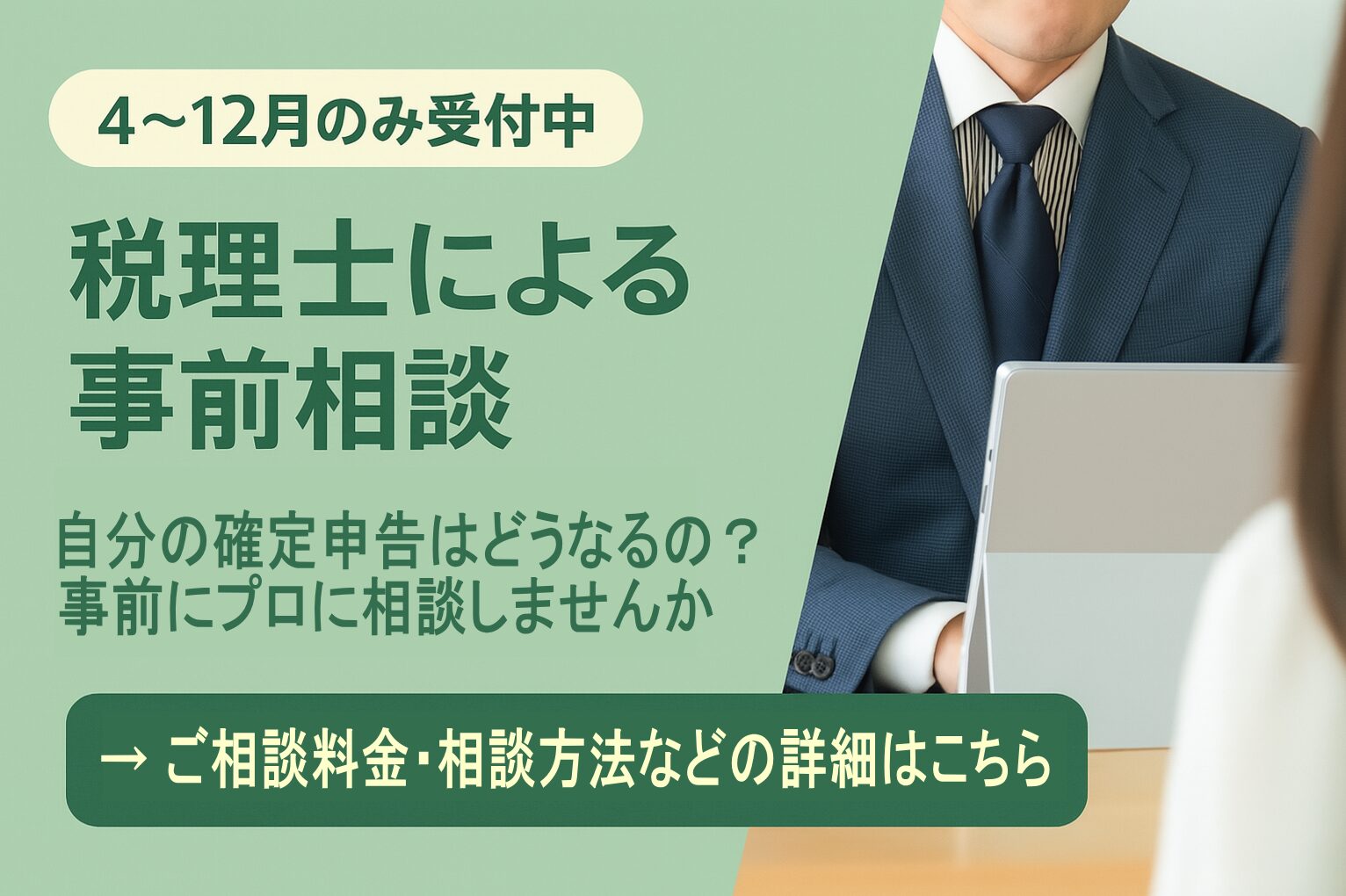「海外に住んでいるから、日本の税金や確定申告なんて関係ない」と思っていませんか?
実はそれ、大きな誤解かもしれません。日本の税法では、非居住者であっても、日本国内に一定の所得を有している場合には、原則として確定申告の義務があります。
この記事では、まず非居住者の定義から出発し、確定申告が必要となる典型的なケースを詳しく解説します。
さらに、申告しない場合にどのようなリスクがあるのか、非居住者の納税管理人制度や申告の流れ、よくある誤解まで、解説します。
海外在住でありながら、日本に収入源をお持ちの方、相続や不動産投資をされている方、退職金を受け取る予定のある方などは、ぜひ最後までお読みいただき、不要なトラブルや損失を回避してください。
非居住者の定義と判断基準
税法上の「非居住者」とは?
非居住者とは、日本に「住所」または「1年以上の居所」がない個人を指します。「住所」とは生活の本拠を意味し、「居所」とはある程度継続して滞在している場所を指します。
日本の所得税法では、これらのいずれにも該当しない人が「非居住者」とされ、日本国内において発生した所得(=国内源泉所得)についてのみ課税対象となります。
居住者との違いと税務上の取り扱い
日本に住んでいる居住者は、日本の国内外すべての所得(=全世界所得)が課税対象になります。
一方、非居住者の場合は、日本国内で発生した所得のみに課税され、国外所得については申告義務がありません。
ただし、非居住者は原則として給与や報酬等に対して20.42%の源泉徴収を受けるため、「もう税金は引かれている」と思っていても、状況によっては確定申告が必要になることがあります。
判定が難しいグレーゾーンの事例
以下のようなケースは、居住者・非居住者の判定が曖昧になりやすく、注意が必要です。
これらの場合は、税務署によって「居住者」と判定されるリスクもあるため、滞在状況や生活実態を明確に記録しておくことが重要です。
非居住者でも確定申告が必要となるケース
非居住者であっても、次のような場合には、日本国内での確定申告が必要になります。
たとえ住民票を抜いていても、「所得が日本で発生している=国内源泉所得がある」場合には、申告義務が発生します。
これらはすべて「日本国内源泉所得」として認識されます。特に不動産所得・配当・退職金などは、源泉徴収されているからと安心せず、内容によっては確定申告による還付や調整が必要な場合もあるため注意が必要です。
源泉徴収だけでは不十分な理由
非居住者に対しては、租税条約による軽減や免除などの例外はありますが、一定の割合(10.21%~20.42%)で源泉徴収が行われることが一般的です。
しかし、それだけで課税関係がすべて完了するとは限りません。
実際には、以下のような理由から、源泉徴収だけでは不十分となり、確定申告が必要または有利になるケースがあります。
源泉課税の仕組みと限界
源泉徴収は、支払者が支払時に税金を天引きする仕組みですが、それはあくまで「仮の精算」です。
源泉徴収された税額が正確とは限らず、過大であることも少なくありません。
また、税金の計算上控除するできる経費や控除が考慮されていないため、非居住者であっても確定申告を行えば税額が下がることがあります。
申告することで節税・還付になるケース
以下のような場合には、源泉徴収された税額よりも実際の納税額が少なくなるため、確定申告を通じて税金を取り戻せる可能性があります。
たとえば、日本株の配当を受け取っている非居住者が、自国との租税条約により10%の軽減税率が適用される場合、源泉徴収された税額の一部を還付してもらえる可能性があります。
所得控除や必要経費・特別控除の適用して確定申告する
不動産収入がある非居住者は、貸すためにかかった必要経費を差し引いて税金を計算することができます。
不動産を売却した非居住者は、取得費や譲渡費用のほかに特別控除を差し引いて税金を計算することができます。
その他、雑損控除、寄付金控除、基礎控除などの所得控除も差し引いて税金を計算することになります。
このように計算した税額を確定申告書上で計算します。
そして、源泉徴収された税額がある場合には、過大に納付した税額がある場合には、還付を受けることができます。
非居住者の申告方法と納税管理人制度
非居住者が日本国内で確定申告を行う際には、国内に住所がある「納税管理人(代理人)」が必要となります。
納税管理人とは?義務と役割
納税管理人とは、非居住者に代わって日本の税務署へ手続きを行う人のことです。
非居住者が日本国内において申告や納税義務を負う場合には、「納税管理人を定めなければならない」とされています。
これは『義務』であり『任意』ではありませんので、注意が必要です。
納税管理人が行う主な業務は次の通りです:
納税管理人は、日本国内に住所がある個人(ご親族や税理士)又は法人に依頼します。
税務署からの問い合わせなどに不安な場合には、税理士へ依頼するのが良いと思います。
納税管理人の選任と届出
納税管理人の選任には、税務署へ「納税管理人の選任届出書」を提出する必要があります。
この届出書には、納税管理人の氏名・住所・連絡先などを記載します。
非居住者の確定申告書
非居住者による確定申告書は、本人である納税者とあわせて、納税管理人の氏名・住所を記載する必要があり、この納税管理人が税務署へ確定申告書を提出するという形式になっております。
税理士以外のご親族などが納税管理人となっている場合には、電子申告ができませんので、確定申告書を税務署へ郵送又は持参により提出することになります。(税理士が納税管理人となっている場合の確定申告は、電子申告が可能となっております。)
投稿者プロフィール

- 盛永 崇也(東京神田で開業している税理士・行政書士事務所の代表)
「税務相談・税務顧問・法人申告・確定申告・相続税申告・相続手続代行・法人廃業代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートしております。
最新の投稿
 不動産売却2025年7月1日非居住者が日本にある不動産を売却したら確定申告は必要?不要?その理由と手続きの税理士解説
不動産売却2025年7月1日非居住者が日本にある不動産を売却したら確定申告は必要?不要?その理由と手続きの税理士解説 海外居住2025年6月24日出国前にやるべき「準確定申告」とは?手続きの流れと注意点
海外居住2025年6月24日出国前にやるべき「準確定申告」とは?手続きの流れと注意点 海外居住2025年6月24日日本に住んでいなくても確定申告が必要なケースとは?【非居住者向けガイド】
海外居住2025年6月24日日本に住んでいなくても確定申告が必要なケースとは?【非居住者向けガイド】 海外居住2024年7月10日非居住者の確定申告(手続き・申告書の提出・納付や還付)
海外居住2024年7月10日非居住者の確定申告(手続き・申告書の提出・納付や還付)